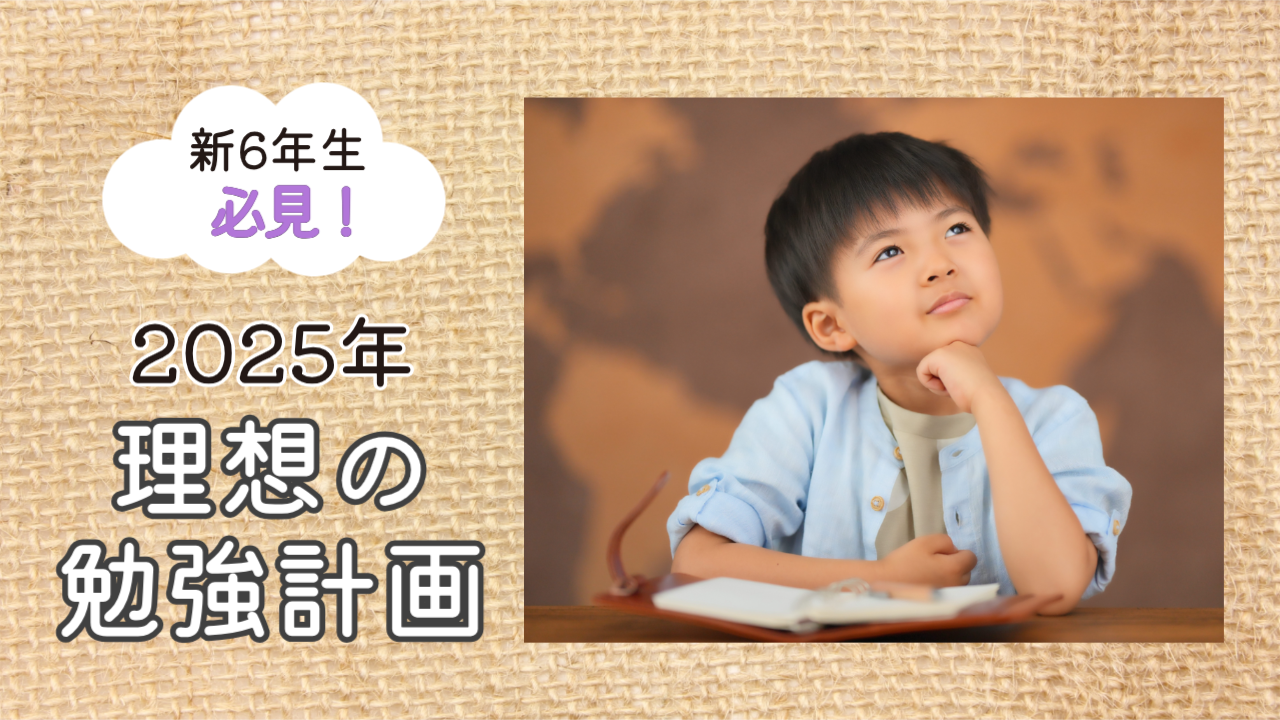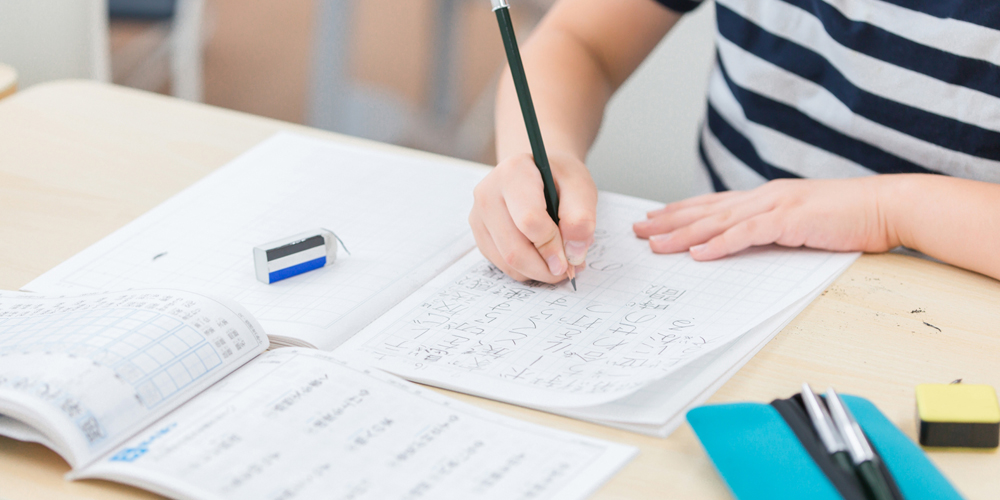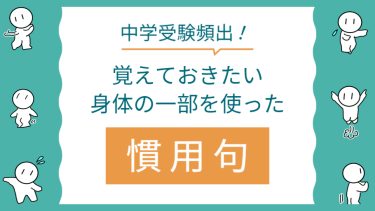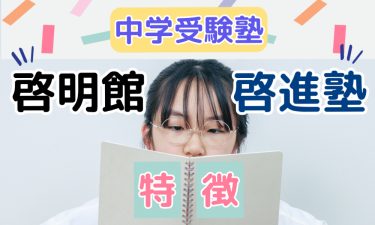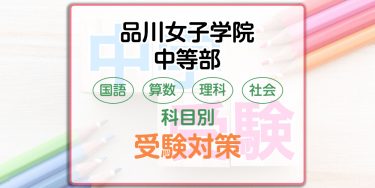新六年生に進級したものの、なにから手をつけてよいのかわからない家庭も多いことでしょう。この記事では、新六年生に向けて理想の勉強計画を紹介します。
大まかに見る新六年生の年間スケジュール

中学受験に挑む六年生は、一年を通してどのように勉強に取り組むべきなのでしょうか。
二月・三月は準備期間
新学期を見据えて、二月・三月はなにから始めればよいのでしょうか。
志望校や併願校を決めよう
志望校を決定します。中学受験本番に向けて、目標を明確にすることは大切です。志望校に受かるためにはどういった勉強が必要になるのかを見定めた上で、一年の計画を立てましょう。
第一志望はチャレンジしてもよいですが、併願校選びは慎重に行います。「志望校に落ちたら公立校に行ってもよい」という子供なら別ですが、基本的には全落ちを避けられるような選び方をしてください。だいたい三校から五校程度受験する子供が多いです。
志望校や併願校選びは塾の先生や家庭教師からもアドバイスを受けましょう。これまで何人もの生徒を見てきた経験を生かし、よりよい組み合わせを考えてくれます。
春期講習を受けよう
塾に通っている子供であれば、春休みには春期講習を受講するのが一般的です。塾ではなく家庭教師をお願いしている場合は、春休みに特化したカリキュラムを受けてください。
塾であれ、家庭教師であれ、宿題がたっぷり出るでしょうから、確実にひとつひとつ片付けていきましょう。並行して苦手科目・苦手単元の克服も欠かせません。
ポイント
志望校や併願校を決定し、勉強の計画を立てると同時に春期講習を受けて苦手科目の克服を進めよう!
新学期から夏休み前まで
新学期が始まる四月から夏休み前まではなにをすればよいのでしょうか。
算数を中心に対策を
六年生の一学期は塾によって、進度の差があります。中学受験の出題範囲の残りを勉強している塾もあれば、すでに出題範囲をすべて終えている塾もあり、その開きは大きいです。レベルの高い塾ほど、先取りで進めて、より受験本番に向けた指導へと切り替えていきます。
いずれにしても、この時期は、算数を中心に取り組む子供が多いでしょう。中学受験において、もっとも苦戦する子供が多い科目であり、勉強した成果が出やすい科目でもあります。
そのため算数を中心に、夏期講習と並行して苦手単元を固めていってください。特に、志望校の頻出単元で苦手単元があるならば、最優先で取り組みましょう。「場合の数」や「平面図形」はよく出題される上、苦手とする子供が多いです。
記述のノウハウを身につけて
苦戦する子供が多い割に、成果が出づらいのは国語です。早いうちからコツコツと対策していく必要がありますし、読書量は多ければ多いほうがよいでしょう。
ただし、読書量が多くて、語彙力や読解力があっても、記述問題は苦手という子供は珍しくありません。記述問題で正答を出すためには要約の仕方や文体、文末表現といった記述のノウハウを身につける必要があります。
ポイント
算数を中心に夏期講習と並行して苦手単元を強化し、記述のノウハウを身につけて国語の対策も進めよう!
夏期講習プラスアルファの夏休み
「夏は受験の天王山」とよく言いますが、六年生の夏休みになにをするべきなのでしょうか。
夏期講習の復習と宿題は徹底的に
塾に通っている子供は連日、夏期講習を受けます。夏期講習では、これまで学んできた内容を広く復習するため、どこができていてどこができていないかを把握することが可能です。
間違えた問題はやり直し、類題にも挑みましょう。夏期講習を「受けっぱなし」にしないことが、受験で結果を出す一番の近道だといえます。夏期講習で学んだ内容はその都度復習しましょう。宿題も手を抜かずこなしてください。自習室があるなら自習室に残ってわからない内容は塾で質問するとよいです。
家庭教師の場合は、子供の進度に合わせて授業を進行していくでしょうから、なにをどこまで進めるか、改めて夏休みが始まる前に先生と話し合っておいてください。話し合った結果は、夏休み中の計画表に落とし込んで可視化しておきましょう。勉強机の前に貼り出しておくことをおすすめします。
漢字や計算も少しずつ
塾や家庭教師の方針によっては、授業の頭に漢字や計算の小テストを実施しているかもしれません。間違えたところは即座に復習してください。
ただ見直すのではなく、次に出題されたときに確実に解ける状態にしておきます。この復習の姿勢があるかないかで大きな差が開くので、日々の積み重ねはとても大切です。
超難関校を受験する人は早めに過去問を
中学受験において過去問を始める時期は基本的に秋ですが、超難関校を受験する人は夏休みから挑戦するケースもあります。なお、志望校のレベルを問わず、子供の多くは過去問を早めにやりたがります。なぜかというと、現時点でのどのぐらいの点数をとれるか興味津々なためです。
しかし、合格ラインの三割以下しか得点できない時期から過去問を解くのは非効率的でしょう。受験校のレベルや本人の実力との兼ね合いを見て、やり込む時期は慎重に決めましょう。ただし、早い段階で問題をざっと見ておいて、出題傾向を把握しておくのは勉強を進める際の参考になるのでおすすめです。
夏期講習と並行して苦手単元をやり込もう
夏期講習の復習や宿題に取り組む一方、夏休みは苦手単元を集中的に勉強するチャンスです。塾や家庭教師と相談し、夏休み中にやり込む単元を絞り込んでおいてください。夏期講習で復習を進めていくうちに「ここが苦手」とわかることも多いので、その都度共有していきましょう。
ポイント
夏期講習の復習と宿題を徹底し、苦手単元を集中的に勉強しよう!
9月から年末に向けてレベルアップ
受験に向けて仕上げていかなければならない秋はどうすればよいのでしょうか。
夏休み後の模試の成績は気にしない
夏休み後の模試で成績が下がってもあまり落ち込まないようにしましょう。夏休み後の模試で一時的に成績が下がる子供は珍しくないためです。夏休みは皆が一斉に頑張る時期なので、成績が変動する傾向にあります。
その成績が継続するかというと、必ずしもそういうわけではないので、もし落ちても「次は取り返す」という気持ちでいればよいです。本人も家族も、あまり深刻に受け止めないでください。
上位校の過去問は九月から
九月になると、上位校を目指す子供たちは本格的に過去問に取り組み、志望校に特化した対策に注力します。多くの場合、初めての過去問の結果は合格ラインをはるかに下回るでしょう。半分以下しかできない結果に、親が大いに焦るのもいわゆる「受験あるある」です。
けれど、この時期は合格ラインの三割できていればセーフと判断します。追い上げるのはここからで、多くの子供が合格ラインに達するのはたいてい冬に入ってからです。
年末で合格ラインの七割程度を目安として考えましょう。ただし、九月の段階で合格ラインの三割未満の場合、率直に言って厳しいです。志望校の変更や併願校の見直しも含めて検討しましょう。
中堅校の過去問は十一月から
中堅校を受ける子供は十一月ごろから過去問に取り組むことをおすすめします。早い時期にやっても解けないですし、それなら十一月に入るまでは解く力をつけたほうがよいためです。
この時期、「過去問をやったところで同じ問題はどうせ出ない」といった嘆きをよく耳にします。たしかに、まったく同じ問題は出ないでしょうが、苦手な箇所がどこかを洗い出せるので有意義です。解けない問題は一問一問潰していきましょう。確実に実力につながります。
実際には、過去問を採点し自分の点数を確認した時点で満足してしまう子供が後を絶ちません。過去問でミスした問題は、自力で解けるようになるまで何回でもやり直してください。「何回でも」というのが大切なポイントで、ひと通り直して次に進むのもNGです。
連日解き直していれば、解き方自体を丸暗記してしまうので、解法を理解できたら間を空けてまた挑むとよいでしょう。
ポイント
この時期は模試の成績に一喜一憂せず、冷静に次の模試に向けて勉強を進めよう!
併せてこの時期からは過去問で志望校に特化した対策を進めよう!
合格に向けた一月・二月
一月は合格ラインに対して九割取れている子供を十割に仕上げる時期です。まだ間に合うので、最後まで気を緩めず追い上げていきましょう。満遍なく復習している時間はもうないので、過去問の頻出単元で不出来なところを集中的にやります。
それ以外にも本番で出題されると予想しているところを中心に、一問一問解けるよう仕上げていってください。勉強時間の確保や感染症対策で、小学校を欠席する子供も少なくありませんが、その辺りは家庭と学校で話し合ってください。
ポイント
最終的な仕上げと集中した学習で志望校合格を目指そう!
全体的なスケジュール
| 時期 | 主な取り組み |
|---|---|
| 2月~3月 | 志望校と併願校選び・春期講習 |
| 4月~7月 | 算数を中心に苦手科目に取り組む |
| 7月~8月 | 夏期講習・苦手科目の克服 |
| 9月~12月 | 模試と過去問を活用して全体的なレベルアップ |
| 1月~2月 | 志望校合格に向けた総仕上げ |
六年生の学習計画を立てる際の注意点

中学受験合格を目指し学習計画を立てる際には、注意点がいくつかあります。
学習計画の内容はひとりで決めない
学習計画を立てる際は必ず先生のアドバイスをもらいましょう。現実味のある効率的な計画を立てるためには、プロの目を通すべきです。学習計画を共有することで先生のサポートも仕方も変わってきます。
多くの塾や家庭教師は、率先して計画を立ててくれるはずですが、計画の内容について疑問に思ったことがあれば、なんでも聞いておきましょう。「なぜそれを先にやる必要があるんですか」「苦手な単元は他にもあるんですが、そちらはどうすればよいですか」といった質問することで、先生も生徒の状況をより詳しく把握できます。
志望校によって、仕上げなければならないレベルは当然変わってくるので、そこの見極めを先生たちにお願いしてください。信頼できる先生に、模試やテストの結果を分析してもらい、志望校に受かるためにはどういう優先順位でいつまでにどこをどうやり込むべきかを整理してもらいます。
どの問題集をいつまでに終わらせるといった大まかな流れだけ決めて、細かな指示はその都度出してもらえるのが理想です。テストや模試などの結果をうけて臨機応変に進めていきましょう。
集団授業だけでは難しいことも
学習計画どおり子供が進めていくのは、ひとりの力だけでは難しいです。間違えた問題をとり纏めて、定期的にやり直させたり、計画の遅れを取り戻させたりするよう働きかける人間が必要となります。
保護者が一手に担うには重すぎる負担です。できれば個別指導や家庭教師といったサービスを活用し、フォローに入ってもらうとよいでしょう。実際、中学受験塾に補習の位置づけのコースを用意している教育サービスはたくさんあります。
後回しになりがちな学習は小テストで
六年生の前半は、算数を中心に、国語の読解、理科の計算に取り組むことが増え、国語の知識問題、理科の知識問題、社会はどちらかというと後回しになる傾向にあります。
しかし、後半でまとめてすべて詰め込むのは大変なので、可能であれば小テストのような形で毎日五分~十分ずつ程度でも知識を増やしていきたいところです。計画に落とし込んでおきましょう。
模試の受け方をよく考えよう
中学受験では四大模試と呼ばれる試験があります。四谷大塚の合不合判定テスト、サピックスのサピックスオープン、日能研の全国公開模試、首都圏模試センターの統一合判です。これらの模試は難易度や受験者の学力に差があるため、偏差値にも開きが出ます。目指す志望校や通っている塾によって、向き不向きがあるのでよく考えて受けましょう。
最難関校を目指すならサピックスオープンですし、標準的な難易度で、レベルを問わず受けやすいのは四谷大塚の合不合判定テストや日能研の全国公開模試でしょう。中堅校以下に向いている統一合判もあります。模試を受ける回数は、六年生の夏休みまでは三、四回ぐらい、夏休み後は毎月一回が目安です。
模試は受けすぎると勉強の妨げになるので、適当な回数受けるのが大切です。
- 先生のアドバイスを受け、計画の優先順位を整理してもらう
- 個別指導や家庭教師を活用して、計画の進行をサポートしてもらう
- 後回しにしがちな科目は、小テストで毎日少しずつ学習する
- 志望校や塾に合った模試を適切な回数受けることが大切
自分に最適な計画を立てて合格を勝ち取ろう!

新小学六年生の一年間はあっという間です。計画を立てて合格を勝ち取るようにしましょう。時期によってやらなければならないことは移り変わっていくので、一年間の流れを把握しておいてください。効果的な計画を作るためには、子供だけではなく、指導のプロの力が欠かせません。
塾講師や家庭教師に相談し、問題点を共有化しながら計画を作成しましょう。志望校のランクによってもやるべき内容や時期は大きく変わってきます。
また、計画を立てた後はフォローする人間が必要です。集団授業だけで、計画を実践するのが難しい場合もあります。そのときは個別指導や家庭教師の力を借りるのもよいでしょう。実際、中学受験塾の補習を行うコースが用意されているところも多いです。
模試を受けて実力を知ることも欠かせません。ただし、模試は志望校によって受けるべき種類があります。また、受ける回数も受験勉強の妨げにならないよう調整しましょう。