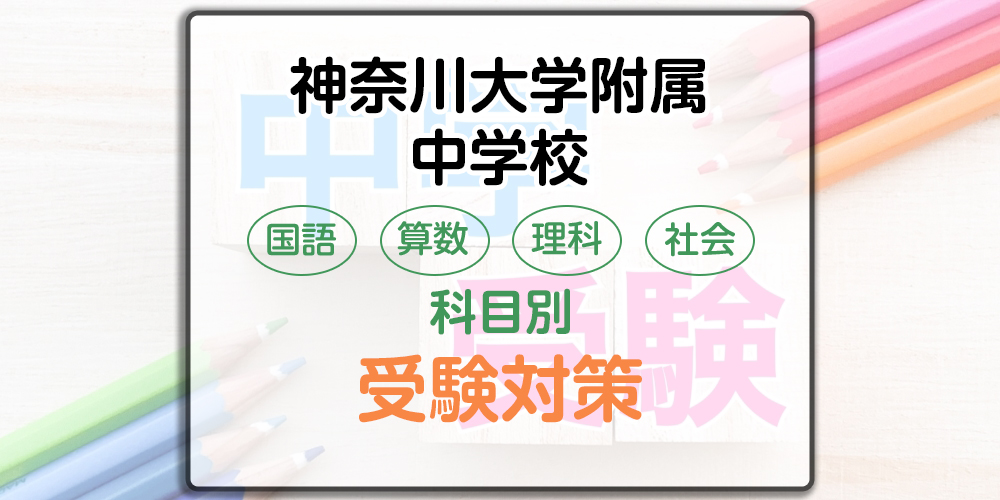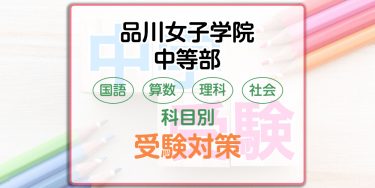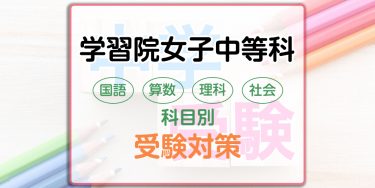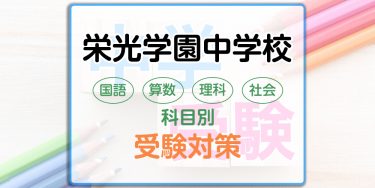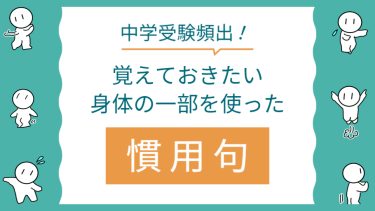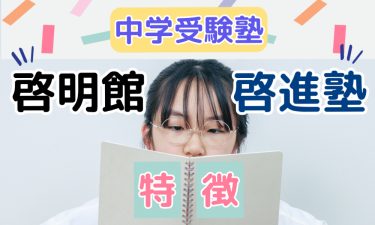神奈川大学附属中学校は、大学の附属校でありながら外部の難関大学を受験する進学校としても知られています。この記事では、神奈川大学附属中学校を目指す家庭に向けて、各教科の出題傾向や勉強法を紹介します。
そもそも神奈川大学附属中学校ってどんな学校?

神奈川大学附属中学校はその名のとおり、神奈川大学の附属校で、完全中高一貫の共学校です。「質実剛健」「積極進取」「中正堅実」を建学の精神として掲げていて、「自ら考え、判断し、行動できる人へ」が合言葉です。一学年は220名ほどで、互いに「認め合い、学び合い、高め合う」関係を築いています。
神奈川大学の附属校ではあるもの、九割の生徒の進学先は外部の大学です。国公立大学、早慶上理、GMARCHを進学先に選ぶ生徒が学年の六割から七割を占めます。神奈川大学への推薦の権利を保持した状態で、大学受験に挑むことも可能です。海外大学推薦制度があり、イギリス、アメリカ、オーストラリアなど9カ国54大学に推薦で進学できます。
2024年度の進路は国・公・私立大学医学部への進学が14名で内現役11名、国公立大学への進学が58名で内現役52名、その中でも東京大学が4名で内現役3名、京都大学が現役合格で1名、一橋大学が現役合格で4名です。海外大学への進学が現役合格で6名、私立大学への進学は883名で内現役839名です。ちなみにその中で、早稲田大学が現役合格で37名、慶應義塾大学が28名で内現役26名という内訳になっています。他には防衛大学に現役で1名合格しました。
進路指導は手厚く、通年あるいは長期休業中の講習、卒業生の学習コーチ、東大生セミナーなどが用意されています。進学のための学習環境も整っていて、「放課後自習室学習支援プログラム」によって、4号館という校舎をまるごと自習室として使用でき、学習コーチによるサポートも受けられます。
よい大学に進学することよりも、自身の進路・進学と向き合うことを通して子供たちを成長させようとしている学校です。一方、個別の生徒を支援するための体制も整えていて、教育相談室(やすらぎルーム)を設けています。心理カウンセラーを週六回配置していて、手厚く対応しているのです
神奈川大学附属中学校の入試概要

神奈川大学附属中学校の入試について見ていきましょう。
2025年度の入試
2025年度の入試日程は、帰国生入試が2024年12月23日にすでに行われていて男女若干名でした。一般入試は、第一回入試が2025年2月1日で男女60名、第二回入試が2月2日で男女120名、第三回入試が2月4日男女20名です。
入学検定料は一回25,000円ですが、第一回入試から第三回入試までを併願した場合は50,000円です。
それぞれの出願期間は、帰国生入試が2024年12月1日(日)10:00~2024年12月18日(水)23:59、第一回入試が2025年1月7日(火)10:00~2025年2月1日(土)6:00、第二回入試が2025年1月7日(火)10:00~2025年2月2日(日)6:00、第三回入試が2025年1月7日(火)10:00~2025年2月4日(火)6:00に設定されています。
なお、出題科目は帰国生入試と第一回入試が国語と算数の二科目、第二回入試と第三回入試が国語・算数・理科・社会の四科目です。
| 入試区分 | 日程 | 募集人数 | 出願期間 |
|---|---|---|---|
| 帰国生入試 | 2024年12月23日(月) | 男女若干名 | 2024年12月1日(日)10:00 ~ 2024年12月18日(水)23:59 |
| 第一回入試 | 2025年2月1日(土) | 男女60名 | 2025年1月7日(火)10:00 ~ 2025年2月1日(土)6:00 |
| 第二回入試 | 2025年2月2日(日) | 男女120名 | 2025年1月7日(火)10:00 ~ 2025年2月2日(日)6:00 |
| 第三回入試 | 2025年2月4日(火) | 男女20名 | 2025年1月7日(火)10:00 ~ 2025年2月4日(火)6:00 |
2024年度の入試倍率
2024年度の中学入試の結果は、帰国生入試が受験者数48名に対して合格者数29名で実質倍率は約1.7倍、第一回入試は受験者数672名に対して合格者数298名で実質倍率は約2.3倍、第二回入試は受験者数665名に対して合格者数212名で実質倍率は約3.1倍、第三回入試は受験者数353名に対して合格者数41名で実質倍率は約8.6倍でした。なお、実質倍率は小数点第二位以下を四捨五入しています。
| 入試区分 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 帰国生入試 | 48名 | 29名 | 約1.7倍 |
| 第一回入試 | 672名 | 298名 | 約2.3倍 |
| 第二回入試 | 665名 | 212名 | 約3.1倍 |
| 第三回入試 | 353名 | 41名 | 約8.6倍 |
神奈川大学附属中学校における国語・算数・理科・社会の出題傾向

神奈川大学附属中学校における一般入試の国語・算数・理科・社会の出題傾向を紹介します。
国語では基本的な読解力や思考力・判断力を問う
国語は、制限時間が50分で配点は100点、大問は三つです。まず大問一で、漢字の書き取りが八問、大問二で説明文の読解、大問三で物語文の読解です。本文はだいたい合わせて7000字から9000字なので、それなりにスピードが求められます。
2024年度は第二回入試と第三回入試の問二・問三で論述問題が出題され、第一回入試のみ論述問題は出ませんでした。そのため、第一回入試のみ選択問題の重要性がより高い構成となっていました。
この第一回入試のみ論述問題が出ない構成は、2024年度からの変更点として学校側が紹介しているので、おそらく2025年度でも同様のスタイルになると予想されます。合格者平均点は第一回が69.2点、第二回が74.6点、第三回が72.1点です。
算数は図形やグラフを重視する傾向
算数は、制限時間が50分で配点は100点、大問は六つです。2024年度は大問一が計算問題、大問二が小問集合、大問三から大問六は単元別の問題で構成されていました。
どの回を受験したかで出題順序が異なりますが、出題単元として「平面図形」「割合と比(グラフ)」「条件の整理」が共通していました。残りひとつの大問ですが、第一回入試では「割合と比」、第二回入試と第三回入試では「規則性」が出題されています。
小問集合は基本・標準的な問題ばかりです。単元別の出題では例年、図形やグラフを重視する傾向にあります。2024年度の合格者平均点は第一回が77.4点、第二回が80.8点、第三回が74.6点です。
理科は各分野からの出題
理科は第二回入試と第三回入試のみで、制限時間は40分で配点は75点です。大問は四つで各分野から出題されます。2024年度は物理、化学・生物・地学の順番でした。実験や観察からの問題が多く、計算やグラフの出題もあります。
基礎・標準の問題中心の出題ですが、応用問題も各分野で一二問出題されます。中には問題文をきっちり読めているかを問うような問題も出ます。合格者平均点は第一回が55.4点、第二回が60.4点です。
社会は基礎知識や事象に関する理解度を問う
社会も理科と同様、第二回入試と第三回入試のみで、制限時間は40分で配点は75点です。大問は三つで各分野から出題されます。
社会は基礎知識の定着化や社会の事象に関する理解度、資料が読み取れるかどうかといった問題です。用語を漢字で書く力や、用語や事象の説明をする力、問題文を丁寧に読み込む力が問われます。合格者平均点は第二回入試が52.9点、第三回入試が49.6点です。
- 国語は漢字や読解問題・論述問題が多く、算数は図形やグラフを重視する傾向にある
- 理科は実験や観察、計算やグラフが出題され、社会は資料を読み取る力が問われる
神奈川大学附属中学校に合格したい。どんな勉強が効果的?

神奈川大学附属中学校に合格するためには、どういう勉強をするべきなのでしょうか。科目別に見ていきましょう。
国語の勉強法
国語にはどう取り組めばよいのでしょうか。
漢字の書き取りは全問正解を目指そう
大問一で漢字の書き取りが出題されるため、全問正解を目指しましょう。漢字の書き取りは「とめ」「はね」「はらい」まで丁寧に書くことが大切です。筆圧も読みやすい濃さを目指しましょう。漢字では同音異義語を書いてしまうミスも発生しがちなので、言葉の意味をきちんと押さえておきましょう。なお、2024年度に点差がついた漢字は「トトウ」「カンレイ」「セッソウ」などです。
速読ができるようにしよう
本文は7000字から9000字で、字数が多めの年度もあるので、最後まで解き終わるよう速読を身につけたいところです。説明文と物語文の両方から出題されるため、分野に左右されず素早く読み込める力を養いましょう。過去問を解いてみて、読む時間と解く時間の配分を確認してください。その上で、自分が読む時間をどのぐらいとれるのか考えます。
第二回入試・第三回入試を受ける場合は論述にも対応できるよう
第二回入試と第三回入試では論受問題も出題されました。論述は子供が苦手とする問題の中でも上位です。書く練習をしておいてください。なお、2024年度は国語の合格者平均点と受験者平均点の点差が大きめでした。つまり、国語が合否を分ける教科だったということです。選択問題だけではなく記述問題でも点をとるためには、常日頃からプロに添削してもらって記述力をアップしてください。
- 漢字は丁寧な字で全問正解を目指し、言葉の意味をしっかりと把握しておく
- 速読できるようにしておくことと、過去問で読む時間と解く時間の配分を確認しておく
算数の勉強法
算数にはどう取り組めばよいのでしょうか。
計算力を身につけよう
大問一の計算問題は例年四問出題されます。全問正しい答えを導き出せるようにしましょう。カッコを使った小数や分数の計算です。ケアレスミスをせず、スラスラ解けるようにする必要があります。
小問集合は全問正解を
小問集合は例年数が多いのでその分、得点になります。(1)から(6)まであり、すべて二問ずつ、計12問です。よく出る問題として損益算、食塩水、平面図形などが挙げられます。基本レベルの問題ばかりなので、各単元の基礎に取り組み固めておきましょう。
小問集合では全問正解を目指したいところです。過去問をやってみて、間違えた問題のある単元は、改めて復習しておいてください。
平面図形は頻出単元
算数では小問集合ではなく単元別の出題でも、平面図形がよく出ます。平面図形の問題はバリエーションが豊かなので、できるだけさまざまなパターンをこなして対応できるようにしておきましょう。平面図形の上を点が移動する問題や、グラフを読み解きながら解く問題もよく出題されるので、類題を解いておくとよいです。
- 計算問題はケアレスミスに繋がりやすい小数分数が多いため、確実に得点を取れるように練習する
- 平面図形は頻出でバリエーションが豊富なため、さまざまなパターンをこなしておく
理科の勉強法
理科にはどう取り組めばよいのでしょうか。
問題文を読み込めるように
理科は読解問題のようなものも出題されているため、注意深く情報を読み込む姿勢が必要です。そのためには時間配分がカギとなります。慌てて斜め読みせずに済むよう過去問に取り組む際には、どのぐらい時間を確保すれば落ち着いて解けるかを確認してみてください。
暗記だけではなく思考力が必要
理科では知識と知識をつなげて考えるような思考力の必要な問題や、複数の分野からの横断的な問題が出題されるため、論理的に考える訓練が必要です。加えて、理科関連の社会問題にも日頃から関心を持っておきましょう。
2024年度では、第三回で学際的な思考力が必要な問題や、科学史的な知識を持っているかが問われる問題が出題されています。
- 過去問で落ち着いて取り組める時間を把握し、時間配分を考えておく
- 知識をつなげて考える思考力が必要になるため、論理的思考を養っておく
社会の勉強法
社会にはどう取り組めばよいのでしょうか。
用語や人物の名称は確実に答えられるように
用語や人物の名称を問う問題が出題されています。漢字表記のものは確実に漢字で書けるようにしておいてください。基礎知識は満遍なく定着化させましょう。また、用語についてはどういう内容を指すのか説明できるようにしてください。
情報を読み解く問題や思考力を必要とする問題も
問題文や資料の中から情報を拾って解く問題が出題されるため、落ち着いて読めるようにしましょう。また、2024年度の第二回入試では、「前年度の入試問題のとある設問で多かった解答」を紹介し、正答として扱えなかった理由を問うなど、変わった切り口の問題が出題されています。過去問を解いて、臨機応変に対応できるようにしてください。
- 用語や人物の名称は漢字で書けるようにし、基礎知識を満遍なく定着させる
- 資料や問題文から情報を読み取って冷静に解く力が求められるため過去問を多くこなす
基礎力の定着化と思考力の育成が必要

神奈川大学附属中学校の問題では、基礎力の定着化と思考力の育成の両方が必要となります。基礎知識を問う問題が多い一方で、ときに受験の定番の枠組みを超えて思考させる問題もまた出題される学校です。
国語では、漢字の書き取りをとめはねはらいまでしっかりと書けるようにしてください。読解の問題は第二回入試と第三回入試では論述が出題されているので、読む力と書く力の両方を身につけましょう。
算数では、平面図形を中心に頻出単元を押さえておきましょう。小問集合は数が多いですが、頻出単元からの出題も多いので、対策しやすいです。
理科は基本的な問題が数多く出題される一方で、横断的な出題の問題もあるので、難しい問題に時間がかけられるようにする必要があります。グラフや図表も多いので読み取れるようにしてください。
社会は問題文や資料から情報を読み取って解く問題が出題されるため、知識問題をスピーディーに終わらせてそちらに時間をかけましょう。変わった問題も出ますが、落ち着いて臨んでください。
各科目の過去問をやり込んで、問題や時間配分のイメージをつかんでおきましょう。