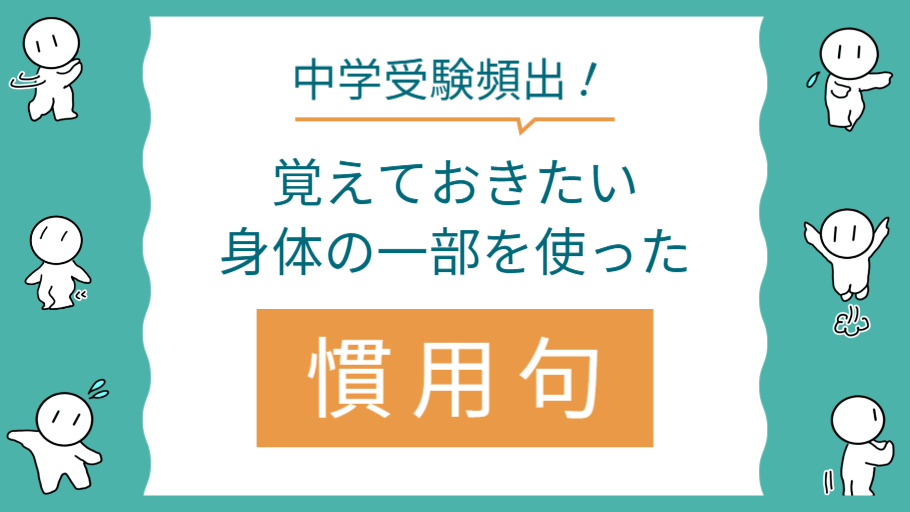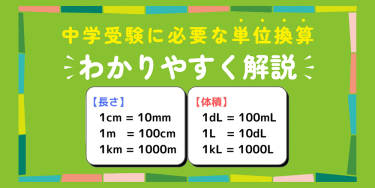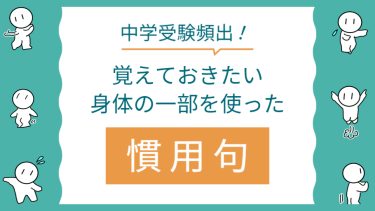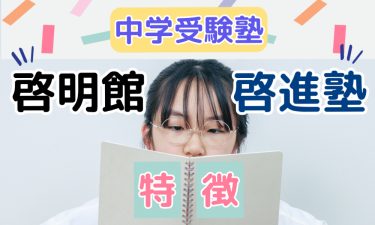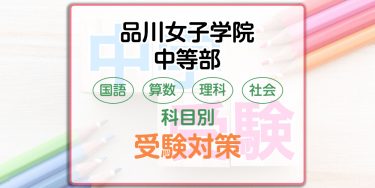中学受験ではよく身体を使った慣用句が出題されます。この記事では子供が覚えておきたい慣用句を紹介します。
身体の一部を使った頻出慣用句
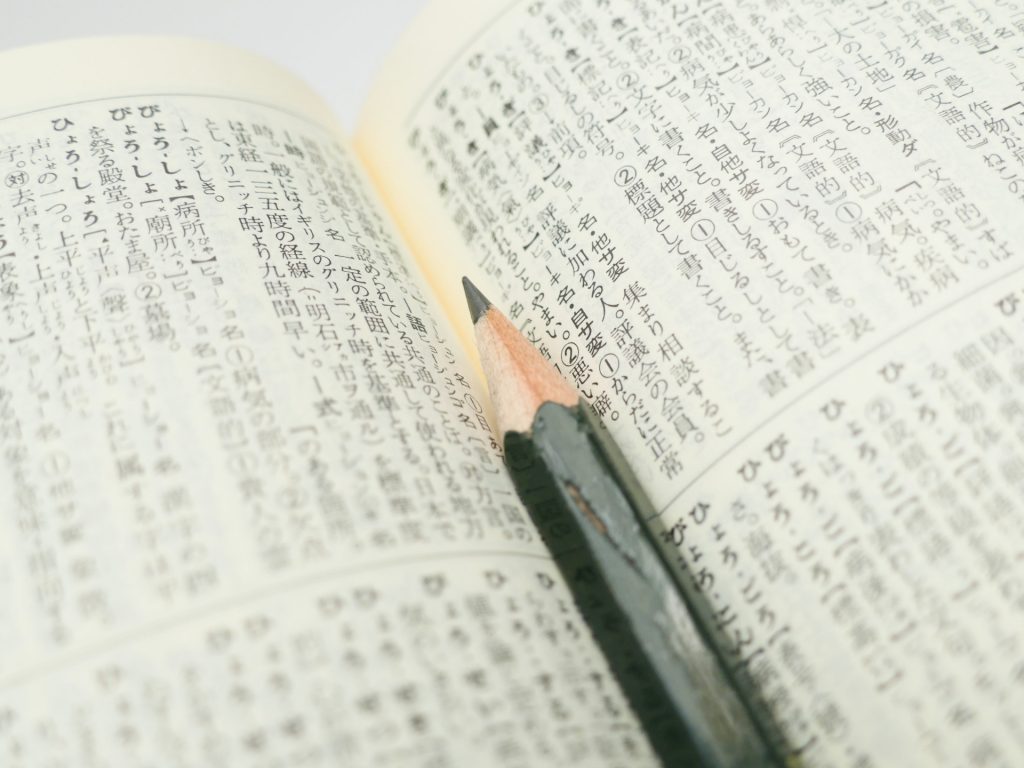
よく出題される慣用句から一部を挙げています。身体の部位ごとに見ていきましょう。
頭に関する慣用句
頭に関する慣用句を紹介します。
頭が上がらない
相手に対して負い目を感じていて、対等にふるまえない様子のことです。
- 山本先生にはずっとお世話になっていて、頭が上がらない
- 宿題を忘れたところを助けてもらって以来、田中くんには頭が上がらない
頭が痛い
解決するのが困難な問題に悩んでいる様子のことです。
- 提出日までに宿題が終わらなさそうで頭が痛い
- テストで合格点に到達できる見込みがなくて頭が痛い
頭が重い
頭が重くすっきりしない様子のことです。悩みごとがのしかかっているときにも使います。
- 寝不足のせいで頭が重い
- 吉田さんには謝っても許してもらえないだろうと思うと頭が重い
頭が固い
考え方に柔軟さがないことです。頑固な相手に対してよく使います。
- 祖父は頭が固く、昔の考え方ばかり押し付けてくる
- 学校のルールは時代に合っていないのに、校長先生は頭が固く、一向に変えようとしない
頭が切れる
頭の回転がはやいという意味です。賢さを評する言葉として用いられます。
- 山田さんは頭が切れ、人気もあるため、二期連続で学級委員に選ばれた
- 谷川くんはのんびりしているようで、意外と頭が切れる
頭隠して尻隠さず
悪事や失敗をすべて隠したつもりで、実際には一部しか隠せていないことを意味します。
- つまみ食いの証拠が口の周りに残っていたため、『頭隠して尻隠さず』と母に言われた
- 『しばらくテストはないよ』と言って息子はごまかしていたが、連絡帳を見ると『明日テスト』と明記してある。『頭隠して尻隠さず』とはまさにこのことだ
頭が下がる
感服するという意味です。相手への敬意を示すときに使います。
- 毎日決められたルーティンをこなすストイックさには頭が下がる
- 常にレベルアップし続ける姿勢には頭が下がる
頭に来る/頭に血が上る
カッとなることです。なお、「頭に来る」のほうは病気や毒が頭に回ること、気がおかしくなることなどの意味もあります。
- 彼の粗暴なやり方は頭に来る
- 図星を突かれて頭に血が上った
頭を痛める/頭を抱える/頭を悩ます
いろいろと心配したり悩んだりすることです。
- あの先生の宿題の多さには頭を痛めている
- 先が見えない日々に頭を抱える
- 今週のスケジュールをどうこなせばよいかで頭を悩ませている
頭を冷やす
興奮した気持ちを落ち着かせて、冷静さを取り戻すことを意味します。
- 怒りで判断力を鈍らせてしまわないよう、頭を冷やす必要があった
- 苛立ちをおさえるのが難しく、一旦その場を離れて頭を冷やした
頭をもたげる
考えや疑念が頭に浮かぶこと。もしくは勢力を得ること、台頭することを指します。「もたげる」という言葉を聞きなれない人もいるでしょう。「持ち上げる、起こす」といった意味合いです。
- あの人が犯人なのではないか、という疑念が不意に頭をもたげた
- 穏健派のリーダーが亡くなったあと、急進派が頭をもたげた
首に関する慣用句
首に関する慣用句を紹介します。
首が繋がる
危ういところで役目から降ろされずに済むことです。
- 失態を厳しく咎められこそしたが、なんとか首が繋がった
- ギリギリのところで成果を出せて、首が繋がった
首が飛ぶ/首になる
解雇されることです。なお、解雇することは「首を切る」「首にする」と言います。
- その年は会社の業績が悪く、多くの社員の首が飛んだ
- 問題を起こした社員が首になった
首が回らない
金銭のやりくりがうまくいかないことです。
- 自分の店を持てたものの、売上が上がらず首が回らない
- 食料品の値上げを受けて、首が回らなくなってきた
首に縄をつける
無理やり連行するという意味合いで使います。
- 首に縄をつけてでも、家出した息子を連れ戻してほしい
- 友達の家に入り浸って帰ってこない弟を首に縄をつけてでも連れ戻したい
首の皮一枚
ギリギリのところで望みが残されていることです。
- 失敗続きの毎日だが、同僚に支えられ首の皮一枚でつながっている
- 首の皮一枚でつながっている状態で、明日どうなるかはわからない
首を傾げる
疑問に思うことや不思議に思うことです。傾げるは「かしげる」と読みます。
- 彼のやり方には首を傾げざるを得ない
- 今になっての方針変更には首を傾げてしまう
首を挿げ替える
重要な役職にある人を交代させるときに使います。
- トップの首を挿げ替えるという決定は今となっては正解だった
- 方針に従わない役員の首を一斉に挿げ替えるという決定に、僕は目を疑った
首を縦に振る
了承することを意味します。
- 思いがけない提案だったが、検討の末、首を縦に振った
- グループから週末の誘いがあり、首を縦に振った
首を突っ込む
興味のある物事に関わることを意味します。
- 部外者が事件に首を突っ込んできた
- 素人がわけもわからず首を突っ込むのは危険だ
首を長くする
待ちどおしい様子を表現するときに使います。
- インターネットで買えた人気商品が届く予定なので、首を長くして待っている
- 自分の順番が回ってくるまで首を長くして待つ
首を洗って待つ
制裁を覚悟するという意味です。
- 『この恨みは忘れない。首を洗って待っていろ』と彼は叫んだ
- 彼のやったことはぜったいに許されない。首を洗って待つべきだ
目に関する慣用句
目に関する慣用句を紹介します。
目が利く/目が高い
ものの価値を見極める力を持っていることを意味します。
- 彼は骨董品にかけては目が利く
- 店主は『この品を選ぶとはお目が高い』と称賛した
目が曇る
物事を適切に判断できないことを意味します。
- わが子可愛さに目が曇る
- 物欲があの人の目を曇らせた
目が肥える
ものの価値を見極める力がアップすることをいいます。
- 親がインテリアにはこだわりを持っていたため、自然と自分も目が肥えた
- 小さい頃から美術館に通っていたため、自ずと目は肥えた
目が冴える
眠気のない状態を意味します。
- コーヒーを深夜に飲んだせいか、すっかり目が冴えてしまった
- 寝る前にゲームに没頭していたせいで目が冴えた
目が据わる
一点を見つめたまま瞳が動かない様子のことです。
- 私の発言がよほど気に障ったのか、据わった目でこちらを見てくる
- 私の言い訳を聞き終えた母の目は完全に据わっていた
目が届く
注意を向けることができる状態を意味します。
- 子供はまだ小さく、私の目が届く範囲にいないと不安だ
- 先生一人に対して生徒の数が多すぎて、果たしてこれでじゅうぶん目が届くと言えるだろうか
目が物を言う
目つきや目配せで意図や心情が伝わることです。
- 彼女はきっとプリンが大好物なのだろう。目が物を言っている
- ひと言たりとも反対しなかった彼女だが、内心は違うのだろう。目が物を言っていた
目から鱗が落ちる
これまで気づかなかったこと、理解できなかったことが急にわかるようになることを意味します。
- 先生からの指摘で目から鱗が落ちた
- 彼女の発言で目から鱗が落ちた
目から鼻へ抜ける
理解力があることを表しています。
- 新しいアルバイトは目から鼻に抜けるような人だ
- 彼は目から鼻に抜けるような人なので、新しい指示内容もすぐに覚えた
目と鼻の先
とても近い距離にあることを示します。
- ケーキ屋はわが家から目と鼻の先にある
- 病院までは目と鼻の先だ
目に余る
黙って見ていられないほどひどいさまを意味します。
- 彼の態度は目に余る
- 彼はその目に余る蛮行を咎めた
目に物見せる
相手をひどい目にあわせて思い知らせることを意味します。
- 次のテストで一位の彼に目に物見せてやる
- この恨みを果たすべく、いずれ目に物見せてやると心に誓った
目の色を変える
目つきを変える様子。怒ったり驚いたり熱中したりする様子をいいます。
- 大好きなゲームソフトを前に彼は目の色を変えた
- 同じ趣味の持ち主とわかった途端、目の色が変わった
目の上の瘤/目の上のたんこぶ
邪魔な存在を意味します。
- 優秀な兄の存在は、彼にとって目の上の瘤だったようだ
- 反対ばかりしてくる直属の上司は、僕にとって目の上のたんこぶだった
目の黒いうち
生きている間のことです。
- 私の目の黒いうちはあの人に好き勝手させないと約束する
- 私の目の黒いうちは、いい加減な真似は許さない
鼻に関する慣用句
鼻に関する慣用句を紹介します。
鼻であしらう
相手の言葉に取り合おうとしないさまです。
- あの男は僕のことを鼻であしらった
- 私の意見は先生に鼻であしらわれた
鼻で笑う
相手を見下して嘲笑することを意味します。
- 彼女は妹の作品を出来損ないだと鼻で笑った
- その人は僕の努力を鼻で笑った
鼻にかける
自慢に思い調子に乗っている態度のことです。
- 彼は実家が裕福であることを鼻にかけている
- 彼女は自身の優秀さを鼻にかけている
鼻につく
匂いが気になること、あるいは人の振る舞いが気に障ることです。
- 香辛料の強いにおいが鼻につく
- あの人の傲慢な話し方はいつも鼻につく
口に関する慣用句
口に関する慣用句を紹介します。
口が減らない
口が達者であることや負けずに言い返してくることを意味します。
- 妹は僕に対しては一向に口が減らない
- 気が小さく口下手な私は、口の減らない弟を半ば感心して眺めた
口が過ぎる
言うべきでないことまで言うことです。
- 彼の怒りはわかるが、先生への物言いはさすがに口が過ぎていた
- よその家庭のことなのに、あまりにも口が過ぎる
手に関する慣用句
手に関する慣用句を紹介します。
手がかかる
手数が必要となることや、世話が焼けることです。
- この料理は意外と下ごしらえに手がかかっている
- 妹はまだ小さいので、手がかかる
手に余る/手に負えない
自分の能力では処理が追い付かないことを意味します。
- この案件は私の手に余る
- あの犬の凶暴さはまったく手に負えない
手を替え品を替え
やり方をいろいろ変えるときに使います。
- 泣く子をあやすため、母は手を替え品を替えなんとか気を引こうとした
- 兄に連れて行ってもらいたくて、手を替え品を替え、機嫌をとった
手を煩わす
人の世話になること、人に負担をかけることを意味します。
- 料理に不慣れな私は手伝いをするつもりが、逆に母の手を煩わせた
- 初参加だったため、他のメンバーの手を煩わせた
足に関する慣用句
足に関する慣用句を紹介します。
足が竦む
緊張したり怖かったりして足が動かなくなる様子のことです。
- お化け屋敷に入る前から足が竦んでしまった
- 近くから大きな悲鳴が聞こえてきて、足が竦んだ
足が出る
予算をオーバーしてしまうこと、もしくは隠し事が明らかになってしまうことです。
- 夕飯は旬の逸品を追加した分、足が出てしまった
- ごまかしていた予定は、SNSに写真をあげたことで足が出てしまった
足が遠のく
よく行っていた場所にあまり行かなくなることを意味します。
- 祖母の家からは、大喧嘩して以来ずっと足が遠のいていた
- 最近あのスーパーは大幅に値上げしたため、足が遠のいてしまった
文章を読みながらその都度慣用句を覚えよう

慣用句は知識として詰め込むのではなく、読解文に出てきたときにひとつひとつ覚えていきましょう。意味を調べて、例文もチェックします。自分でも使いこなせるように例文と合わせて覚えるようにしてください。
類似する意味の慣用句も一緒に覚えておくとよいです。語彙を増やす機会を大切にしてください。慣用句やことわざといった語彙は、受験直前に詰め込んで丸暗記をするには数が多すぎますし、例文と一緒に覚えないと生きた言葉として定着しないため、あまり意味がありません。
「顔に関する慣用句」や「目に関する慣用句」が代表例ですが、ひとつの部位だけでたくさんの慣用句があります。一気に詰め込もうとすると、どれがどの意味だったか混同してしまうので、読解を通して語彙力アップに取り組むようにしてください。低学年のうちから読解文で出てきた慣用句はその場で覚えてしまうよう習慣づけることをおすすめします。